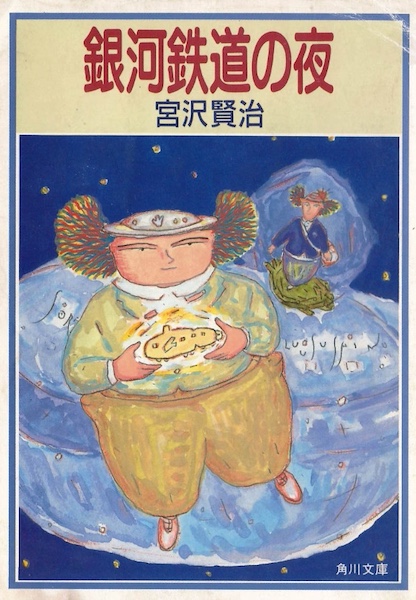
筆者の読んだ角川文庫版
(平成2年 改版第64版)
2024.12.21
スマホ向け:記事カテゴリ一覧を跳ばす2024年の12月、筆者は『銀河鉄道の夜』を題材とするコンサートに出演した。そのおり、これを好機と初めて原作小説を通読した。宮沢賢治作品はいくつか読んでいたが、『銀河鉄道の夜』は未読だったのである。
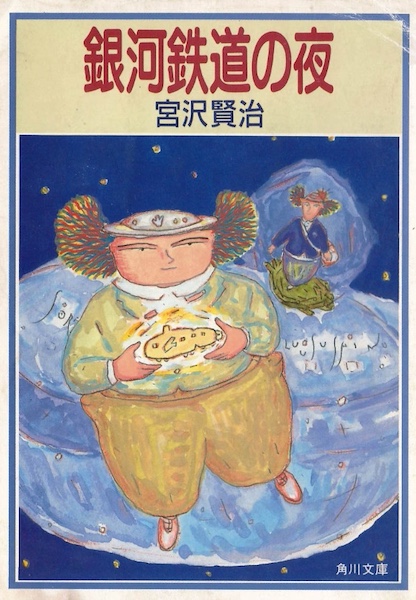
筆者の読んだ角川文庫版
(平成2年 改版第64版)
一読して驚いた。銀河鉄道の原作中において、この鉄道の動力車は蒸気機関車ではないと明確に書かれているのだ。銀河鉄道の夜といえば、筆者にとって蒸気機関車のイメージであった。書籍の表紙絵を含む、あまたのイメージビジュアル、あるいは本作の本歌取ともいえる『銀河鉄道999』、そして擬人化ならぬ〝擬猫化〟のアニメーション映画版(杉井ギサブロー監督作品(1985年)、ますむらひろし氏の漫画(1983年)を原案とする映像化版)などのいずれでも銀河鉄道は蒸気機関車がシンボリックに描かれる。しかし原作では否定されている。本文における該当箇所はこうだ。
「この汽車石炭をたいていないねえ」ジョバンニが左手をつき出して窓から前の方を見ながら言いました。(角川文庫版(1969年)、p.189)。
筆者は驚いた。こうはっきり書かれているのに、かくも蒸気機関車のイメージで世間は銀河鉄道を理解しているのだ。もちろん、原作を読む以前の筆者もそうであった。銀河鉄道といえば蒸気機関車。ノスタルジックな蒸気機関車こそが、宮沢賢治の空想世界の鉄道にふさわしいと。だが賢治の生きた時代において蒸気機関車はノスタルジックでも何でもない日常の一部だ。だから銀河鉄道という言葉に対して蒸気機関車を連想するのは、後世を生きる我々の勝手でしかない。
ジョバンニは何のために「左手をつき出して窓から前の方を見」たのか。煙を探したのである。煙(と蒸気)が客車の窓際へ流れてきていないことを確認していたのであろう。筆者のSL乗車体験はわずか1回、栃木県にある真岡鐵道が走らせている「SLもおか」(C12形蒸気機関車)だ。風向きと乗車した席にもよるが、たしかに窓から煙を確認できたと記憶している。さて、では銀河鉄道の動力車の正体はなんなのだろう。原作には次のように書かれている。先ほどの引用箇所を含めて続きを示す。
「この汽車石炭をたいていないねえ」ジョバンニが左手をつき出して窓から前の方を見ながら言いました。
「アルコールか電気だろう」カムパネルラがいいました。
するとちょうど、それに返事するように、どこか遠くの遠くのもやのもやの中から、セロのようなごうごうした声がきこえて来ました。
「ここの汽車は、スティームや電気でうごいていない。ただうごくようにきまっているからうごいているのだ。ごとごと音をたてていると、そうおまえたちは思っているけれども、それはいままで音をたてる汽車にばかりなれているためなのだ」(同、p.189-190)
つまり、銀河鉄道の動力(機関)車は正体不明である。〝ただ動くように決まっているから動く〟というから驚きだ。物理(運動)の法則によってではなく、〝動く〟という事象のみに原因と結果を一体化させて走っている。スチーム(蒸気)ではなく、電気でもない。電車ではないし、もちろんディーゼル車でもない。もっと神秘的な力で動いているのである。
ジョバンニは、ジョバンニの母との会話において「カムパネルラのうちにはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを七つ組み合わせるとまるくなって、それに電柱や信号標もついていて信号標のあかりは汽車が通るときだけ青くなるようになっていたんだ」(同、p.179)とも語っている。
「七」という数字と「円環」が何の象徴であるか、どう読み解くかは本稿の趣旨から外れるので脇に置く。要点は、おもちゃの機関車という豪華な遊び道具をカムパネルラは持っていて、ジョバンニの印象に深く刻まれているという点だ。乗った汽車が蒸気機関車ではないと言うジョバンニに対してカムパネルラが「アルコールか電気」と答えるのは、このことが伏線となっているのであろう。このシーンは、カムパネルラの家は経済的に恵まれている一方、ジョバンニの家庭の貧困状況を語るコントラストとなっている。筆者も小学校低学年の頃、たくさんのNゲージを持っている友人を羨ましく思ったものだ。筆者も父にNゲージをせがんだことがある。父はNゲージのカタログ本を買ってくれ、筆者はカタログ本をじっくり眺めながら、空想の中でそれらの電車を走らせた。
言うなれば、丘の上で眠ったジョバンニの夢の中に、カムパネルラの持っていた「おもちゃの汽車」が現れ、ジョバンニはそれに乗ったのだ。その汽車はジョバンニにとって憧れの象徴であると同時に、賢治にとっても電車は近代科学と産業の産物、かつ同時に生活に結びついた乗り物でもあった。現代でもドイツでは、アルコールランプで水を沸騰させて蒸気の力で動力を起こす教育玩具が売られている(参考ページ)。カムパネルラの持ち物として登場したそれは、賢治が実際に目にしたことのあるおもちゃだったのだろうと筆者は推測する。
さて、そのような神秘的な動力源で動く銀河鉄道の車両は、どのような外観をしているのだろうか。銀河鉄道の客車内で、ジョバンニとカムパネルラは、その座席から動かない。本文から感じられる座席のイメージは、2名掛けのシートが向かい合った4名用のクロスシート(いわゆる「ボックス席」)だろうか。長距離を走る客車において定番と思えるレイアウトだ。現在も郊外を走る列車の多くで見られる。筆者は都市圏生活者のため、クロスシートを見ると旅情を感じる。
銀河鉄道の沿線のモデルとされているのは、岩手軽便鉄道である。この鉄道路線では蒸気機関車が走った。これが映像化において銀河鉄道を蒸気機関車で描く根拠となっているのはうなづける。とはいえ、本文中にて蒸気機関車は否定されているのであるから、別の動力車を想定すべきだろう。
第2の候補とされているのが花巻電鉄である。これは路面電車と鉄道の両方を持つ路線だ。だから『銀河鉄道の夜』のような長距離の鉄道旅行の雰囲気とのミスマッチは否めない。しかし賢治が実際に利用していたであろう電車はこれであるから、銀河鉄道が電力駆動でないとしても、石炭車などがないと明記されている以上は列車の見た目として電車を想像するのが適切ではないか。だが、車体はそれほど大きくない。古い写真を見るとロングシートの仕様である。
これらの前提に立ち、筆者は、銀河鉄道の見た目は、車体の細い路面電車よりも現代の電車にもっと近く、しかしそれでいて「レトロ的な外観」を保ち、かつクロスシートが十分に配置可能と思われる電車がふさわしい。筆者はそれらの条件を考えて江ノ島電鉄の車両などを想像する。つまり、「銀河鉄道の見た目は江ノ電あたりではないか?説」を筆者は提唱する。
江ノ電の車両はロングシートであり、クロスシートを置くには狭すぎる。だが、ご想像いただきたい。一回り大きい江ノ電の車体にクロスシートが2列で並び、「銀河ステーション」のアナウンスが流れ、少年たちを乗せて天の川に沿った鉄道の旅をする姿を。車両は2両編成であろう。運転士と車掌が同乗する。電車は南十字へと走って行き、ついに「石炭袋」を過ぎたところでカムパネルラは姿を消す(p.236)。
筆者は本作を読み始めてすぐに、祭りと川遊び、少年たちの行動、ジョバンニの母との会話などを伏線として、本作が悲劇であろうと察した。それまで勝手にいだいていた、楽しげなファンタジー作品であろうという本作への先入観は、ジョバンニが丘で眠りに落ちる頃には雲散霧消していたのである。あとの展開は本作の読者諸兄もよく知るところだ。『銀河鉄道の夜』は静かな悲劇であり、厳かな宗教劇としての性格も持つ。本作は、弔いであり、文学の形をとった鎮魂曲〈レクイエム〉といえるだろう。
筆者が本作を通読して感じたもう1つの謎が、本作を流れる「新世界交響楽」の正体だ。
クラシック音楽を知る人ならば、ドヴォルザーク作曲の交響曲第9番「新世界より」(From the New World)がその音楽作品であることはすぐにわかる。だが、劇中で語られる「新世界交響楽だわ」(p.223)において、この音楽の、どの部分が賢治の頭の中を流れていたのだろうか。
ドヴォルザークは旋律を生み出す能力において、天才的な才能を持った作曲家であった。「新世界より」においても、いくつもの旋律(音楽の用語では旋律を分解して「動機(motive)」、動機のひとかたまりを「主題(theme)」と呼ぶ)が登場する。全4楽章で構成される「新世界より」にも、全楽章を通すと7つの主題が含まれる。このどれが銀河鉄道の中盤で流れる「新世界交響楽」なのだろうか。
「新世界より」を通して演奏すると、約40分ほどかかる。ジョバンニたちの旅の中盤から、「新世界より」の全楽章が流れたとしても不思議ではない。となると、途中乗車する「かおる子」のセリフにある「新世界交響楽だわ」の場面には、何楽章のどの主題が当てはまるのだろうか。
その特定(同定)は賢治研究者による推定に委ねるほかない。筆者はクラシック音楽ファンとして、また銀河鉄道の情景においては、特定の旋律が1つだけ流れたのではなく、旋律から受ける心象が重ね合わされているのではないかと想像する。つまり「この場面では旋律Aが流れた」という1対1の同定ではなく、「この場面には、旋律A、B、C、D、E⋯⋯などから受ける心象風景の総合が層になって積み上がっているのではないか」というわけである。つまり「新世界より」の聴衆が受ける音楽体験の総体として表現されているのが、かおる子の「新世界交響楽だわ」ではなかろうか。これは映像では表現できない。文学だからこそ表現できる四次元的(あるいは五次元以上か?)な詩的解釈であろう。
新世界交響楽はいよいよはっきり地平線のはてから湧き、そのまっ黒な野原のなかを一人のインデアンが白い鳥の羽根を頭につけ、たくさんの石を腕と胸にかざり、小さな弓に矢をつがえていちもくさんに汽車を追って来るのでした。(p.224)
『銀河鉄道の夜』に謎は尽きない。未完の作品として、解釈の旅を読者も続けるほかないのだ。銀河鉄道の旅は、そのように読者の自由な空想に任された旅なのであろう。
ますむらひろし氏のインタビュー記事によると、氏も最初はボックス席で描いたが、のちの版ではロングシートに描き直している。その経緯を次のように説明している。
「賢治は列車の音を“ごとごと”と書いた。“ごとんごとん”じゃない。それはつまり、線路の幅も狭く車両も小さいから“ごとごと”なわけで、軽便鉄道という小さな列車であることを示しているんです。すると、最初はボックスシートで僕は描きましたが、軽便鉄道はロングシートで、これは描き直さなきゃいけないな、となる。」
(「なぜ、ますむらひろしは宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』を幾度も猫で描くのか」 『BRUTUS』Web版 2023.4.10)
筆者は本稿を書き終え、関連画像を収集する過程で次の論文と出会った。
『『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」 : その動力源はなにか』(家井美千子, アルテス リベラレス (岩手大学人文社会科学部紀要)第93号 2014年3月 15頁〜31頁)。この論文の著者も「銀河鉄道=蒸気機関車の鉄道」と読むことは不適当である」とし、筆者と同じくジョバンニのセリフから蒸気機関車説を否定する。
「軽便鉄道であることを確認後ジョバンニが行ったのは,「左手をつき出して窓から前の方を見」ること(引用②)だった。これは,手を窓の外に出すことによって蒸気機関の出す煙が流れているかを確かめ,さらに夜ではあっても見えるかもしれない煙を目視しようとしたのであろう。その結果が,「この汽車石炭をたいてゐないねぇ。」という発言だったのだ。」(同 PDF p.3 / 表記ノンブルp.18)。
さらに著者は車内の静けさに着目している。
「蒸気機関の特徴は,先にあげた煙の発生に加え,蒸気の放出音や重い車体を動かすための外燃機関から発せられる大きな機械音である。つまりは大きな騒音を伴う乗物であるのだが,「銀河鉄道」の特徴はむしろ静謐な乗物であることをこれらの引用から理解できる。蒸気機関の音がしていたのなら,カムパネルラも「さびしさうに星めぐりの口笛を吹」いたりはできなかっただろう。
このように,ジョバンニとカムパネルラの会話内容と「銀河鉄道」の描写から,『銀河鉄道の夜』のジョバンニたちの乗った「銀河鉄道」は,蒸気機関に牽引されたものではない,ということが明らかである。」(同、p.4)
「なによりも,『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」の静かさは,電車に乗った時の印象に大変近い。
電車は機関車に牽引されていないから機関車の出す轟音は聞こえず,ただ発車の合図の後に静かに動き出すものである。そして走行の間に聞こえるのは,レールの継ぎ目を通過する時の「ごとごとごとごと」という音だけである。これは,『銀河鉄道の夜』で「銀河鉄道」が描かれる時の描写にぴったり当てはまっており,「銀河鉄道」は電車である,と考えても何も問題はないように思われる。(中略)
いずれにしても,『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」は,電車に乗った時の体験に非常に似通ったものとして描かれていることは間違いなく,それは実際に賢治に花巻電気軌道の乗車体験があったからである。
なお,花巻電気軌道も軽便鉄道であり,軌道幅が岩手軽便鉄道と同じであったため,最初期には岩手軽便鉄道で使用していた蒸気機関車で客車を牽引したことがあったというが,それ以外はすべて電車であった。これに対して,岩手軽便鉄道は,最初からずっと蒸気機関による牽引であったのである。」(同、p.14)
〈おわり〉
参考文献
『銀河鉄道の夜』宮沢賢治 角川文庫 1969年
※本書収録の『銀河鉄道の夜』について、次のように説明されている。
昭和四十四年完結の筑摩書房版第二次宮沢賢治全集第十巻の本文を基とし、その表記を新字、新かなづかいに改めたものが本書の形になっている。
『なぜ、ますむらひろしは宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』を幾度も猫で描くのか』 BRUTUS Web版 2023.4.10
『『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」 : その動力源はなにか』(家井美千子, アルテス リベラレス (岩手大学人文社会科学部紀要)第93号 2014年3月 15頁〜31頁)