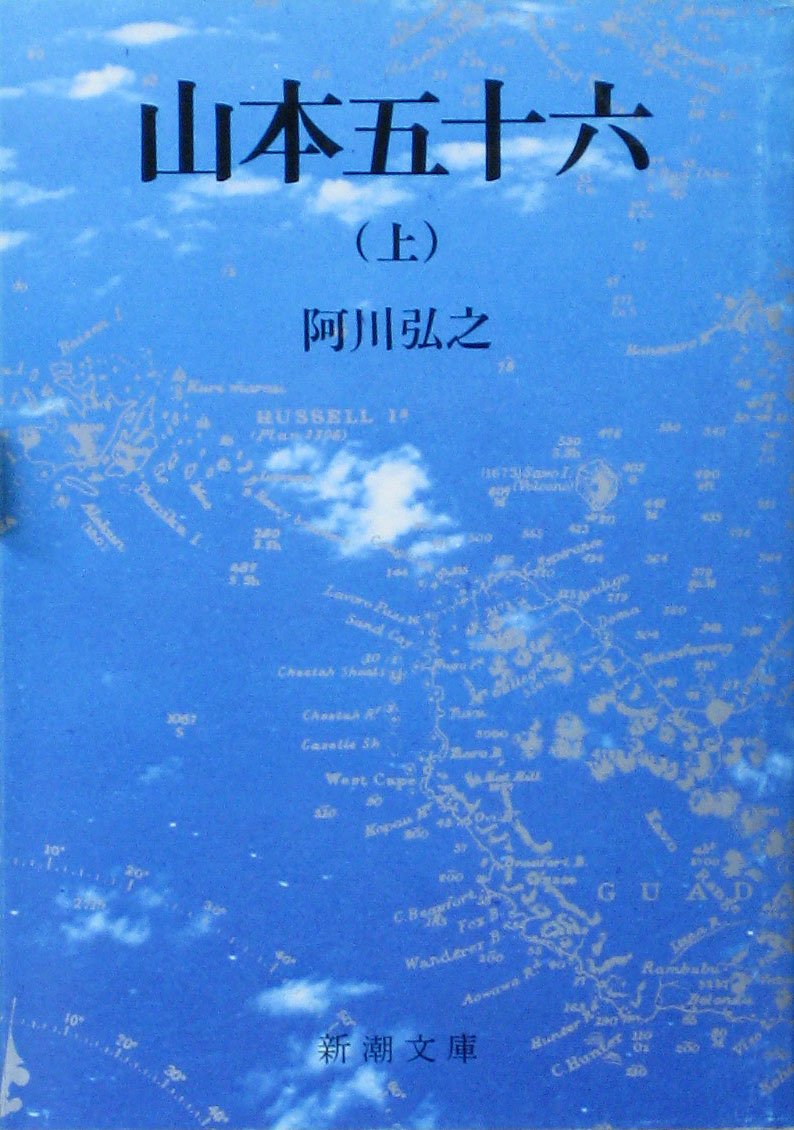
『山本五十六』文庫版上刊
2024.12.19
スマホ向け:記事カテゴリ一覧を跳ばす太平洋戦争を指導した旧日本海軍の首脳陣について書かれた本を集めると書架が何台埋まってしまうだろうか。当事者本人によって書かれたもの、同時代の関係者がその目で見たものを著したもの、戦後に世に出た記者や作家によって先行資料や伝聞がまとめられて世に出たもの。その量は膨大だ。戦史研究者や軍事マニアなどでない限りとても一般の読書人が読み切れるものではない。だから何を読むべきだろうか? その取捨選択が重要だ。
読書人の読みたい、知りたいという欲求に十分に応えうるだろうという観点で選ぶならば、私は阿川弘之の『山本五十六』『米内光政』『井上成美』の通称「提督三部作」が、その期待に応える本だと考える。半藤一利や戸部良一などの数々の労作と並行して私も読んだ。阿川の提督三部作についての感想を述べたい。
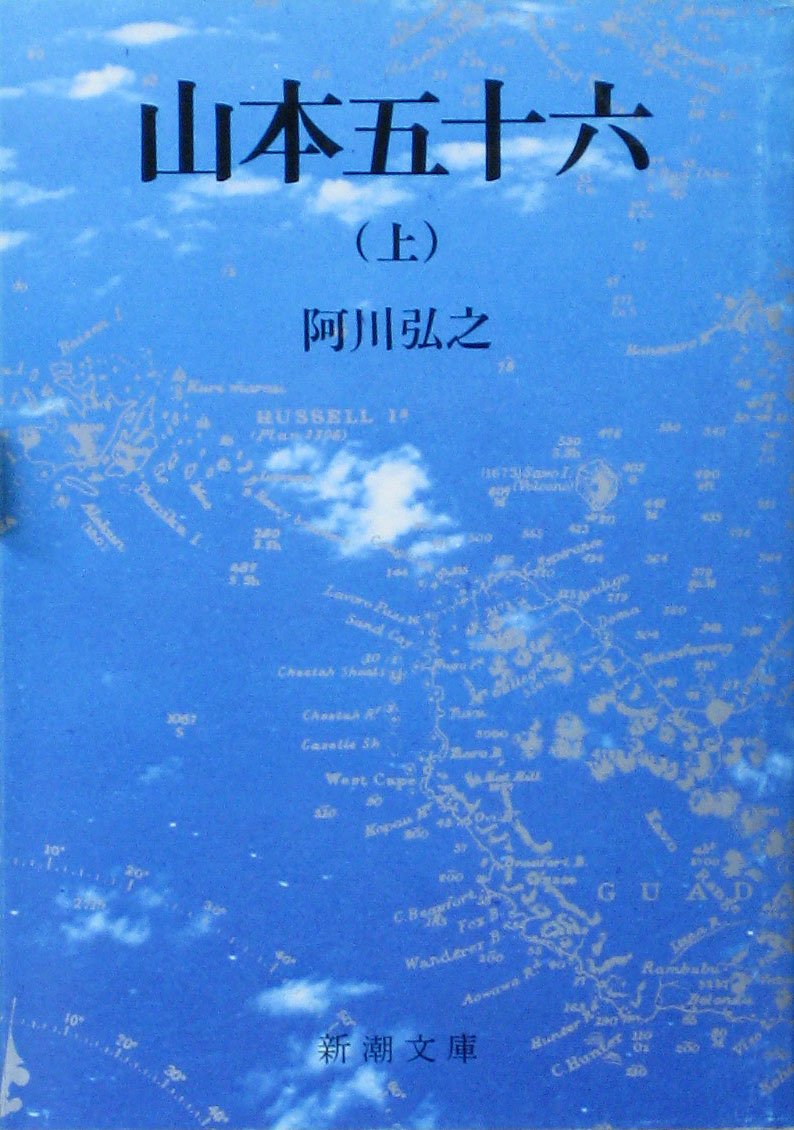
『山本五十六』文庫版上刊
本作を読むならば、新潮文庫版(昭和48年刊)をお勧めする。最初に刊行された単行本版(これもすでに雑誌連載版から加筆修正されているのだが)に追加の調査・取材の成果が追記されたうえで文庫化されているからだ。
阿川と山本は対面していない。阿川が海軍予備学生として入隊した昭和17年9月の翌年、阿川の少尉任官(18年8月)の4カ月前(18年4月)に山本は戦死している。海軍甲事件である。阿川は朝日新聞社の海軍担当記者、杉本健の紹介によって井上成美と石川信吾との知己を得て本書執筆に取り組んだ。本書は資料と関係者インタビュー取材に基づいて執筆されているがゆえに、阿川が精緻な筆致で書き進めていても、伝聞を咀嚼して再構成した匂いはぬぐえない。
だが新版の文庫化にあたり、阿川は山本の戦死地ブーゲンビルの現地取材を敢行している。阿川が自分の目で確かめてきた現地に関する内容へ進むと、俄然、内容への焦点が鮮明になり、解像度が飛躍的に高まっている。これが取材のリアリティだ。阿川が本書を書くにあたり、どれほど膨大な取材ノートを作ったのかはわからないが、おそらく写真や図画といった資料も相当量を集め、見比べて仔細に検討したであろうことが想像できる。
本書の面白さとして、山本の人間関係を独自の視点で容赦無く描き出していること、特にその同僚との関係や女性関連のことは特筆したい。ゆえに山本を軍神として信奉する郷里の方々から強烈に批難されたと阿川は書いている。読者として想像に難くない。私は阿川は恐れ知らずなのかと、本書後半を読みながら唸った。
山本に関する本は専門の研究者によるものから一般向けの安易な読み物まで膨大であり、ひとつの山のようだ。 よって山本について多くを知りたい読者の要求に十分に応える質と量を備えている。阿川の著作はその中のひとつの秀峰として、手に取るべき1冊だ。
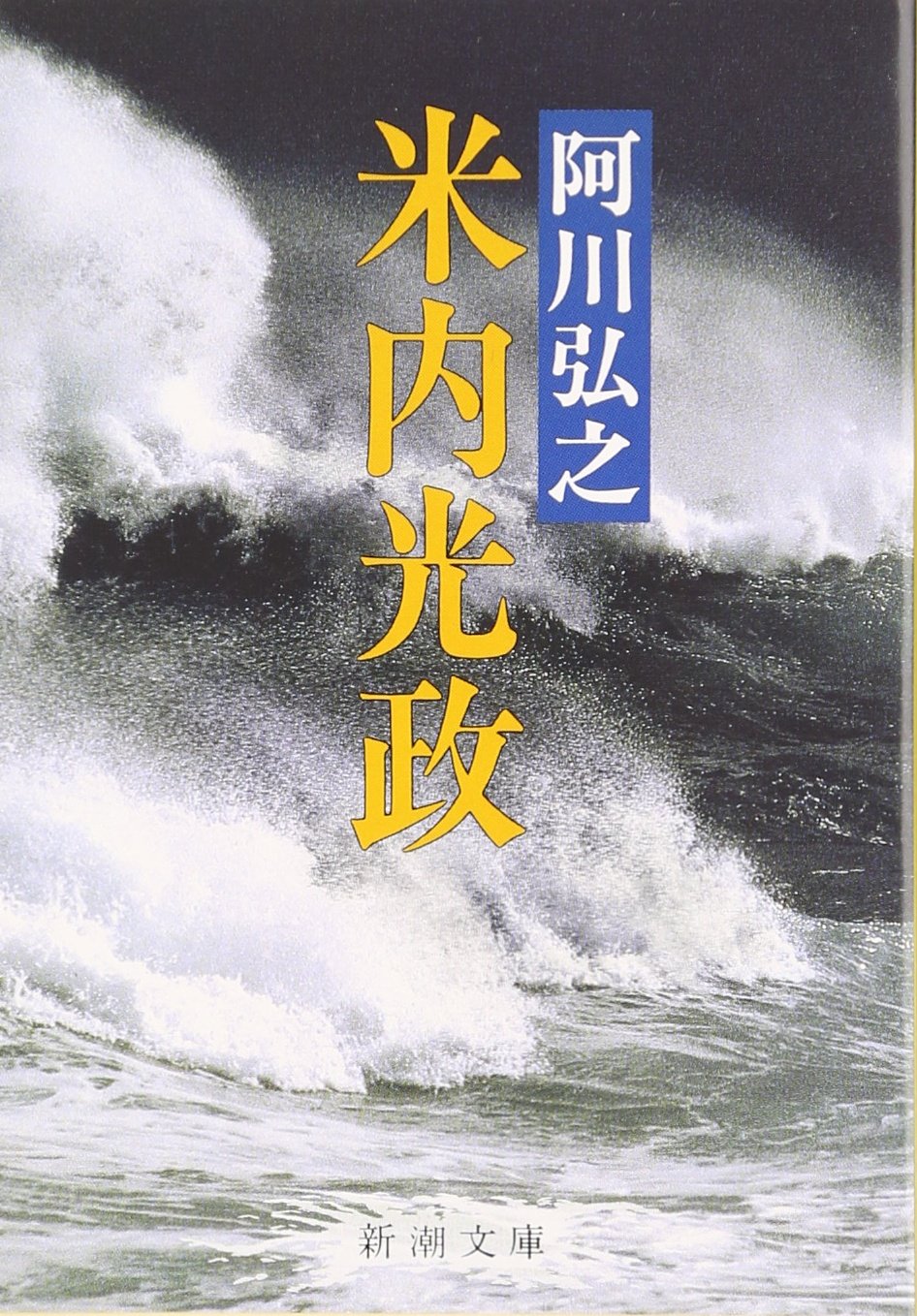
『米内光政』文庫版
昭和57年刊行の文庫版が今も版を重ねているのかわからないが新刊書店でも入手可能だし、古書店でも容易に見つかる。『山本五十六』が多様な角度で取材された話の集大成に思えた一方で、阿川の『米内光政』では一本の大道が敷かれた上で、順次、しっかりとしたエピソードが展開されていくように感じられた。それはひとえに、米内が終戦に直接関与するという役割を果たしていることも関係しているだろう。終戦に関与していない山本と比較して、前者をエピソードの拡散と捉えるならば、米内には終戦という歴史の収斂ともいえる日々がある。これを避けることができない以上、本書がそうした構成になったことは自然だ。
歴史関連の本を好む読書人にとっても、戦争遂行の上り坂にいた山本と比べ、戦争終結に向かっていく過程で表舞台に出てくる米内は、名前こそ見ていても、「歴史上の人物」として山本ほどの印象は残りにくい人物だろう。とはいえ、米内と直接対面した人々にとっての米内の印象はまったく異なることを、本書を通じて強く感じる。
本書は米内についてのエピソード群を巧みに編纂して著されているが、一方でエピソード集のような印象を拭いきれない。とはいえ、一とつひとつの内容は迫真である。以下、その例を示す。これらの抜書きに興味を持たれた方には、本書は非常に面白い一冊になるだろう。米内を追っていく本書と比べるならば、半藤一利の『聖断 昭和天皇と鈴木貫太郎』(2003年刊、2006年文庫 PHP研究所)では米内は数えるほどしか登場しない。そうした比較も読書の面白みだと思う。
「心はこれ身の王。王に威ありて国泰(やす)し。心を尊ひ心を養ふ。その徳即ち身に現す。疫癀(えきれい)もこの人を襲はす毒蛇もこの人を螫(さ)さす。昼は煩(わづら)いなくて居泰く、夜は夢なくして眠り隠なり」云々。
正木は知らなかったが、法華経の研究家で哲学者の小林一郎が成蹊学園の設立趣旨をしるした「こころの力」という書物からの引用で、これに米内の走り書きのメモがクリップで留めてあり、メモには、
「人の信仰対象に対する態度は綜合(そうがふ)の態度であるといふ。信仰対象を分析してその帰依すへき理由、渇仰(かつがう)すへき理由を知りて然る後帰依し渇仰するのではないそふです。故(ゆゑ)に信仰対象に就て必しも正確な知識を有(も)たないといふことであります。(中略)君は一笑に附するかも知れんが読んで下さい」
と書いてあった。(p.46)
遥拝式が終わると、艦に残っている准士官以上、第礼服を通常礼装に着替え、士官室に揃って司令長官の年頭の訓示を聞き乾杯をする。長官訓示というのは通例、
「新年の嘉節にあたり、国運の益々隆昌ならんことを祈念し、艦隊将兵一同帝国海軍の使命の重且つ大なることを思うて」
と、長ったらしいものだが、米内は支度の出来た士官室に副官を従えてつかつかと入って来ると、
「只今より聖寿の万歳を三唱する。天皇陛下万歳」
つづいて、
「乾杯」
酒がちょっとこぼれた。白いハンカチを出して軽くそれを拭い、自分で注ぎ直し、もう一度杯を挙げて、
「諸君の健康を祝す」
一と息に飲み乾すと、身を翻してさッと退場していった。(p.175)
「先任副官、君は芸者にもてるコツを知ってるか」
と、深夜突然米内が言い出した。
磁石が鉄片を引き寄せるように人を惹きつける魅力を備えた人だとかねて思っていたが、これには驚いて、
「はあ?」
と聞き返すと、
「それはネ、わけ無いんだ。人間誰しも弱味があるが、彼女たちはたいてい貧しい家庭に育って、身辺に色々複雑な事情があって、暗い過去をしょっているからね。それに触れないようにしてやることだよ。触れずに同情をもって、おもちゃ扱いしないで、彼女らの人格を認めてやるようにしてればもてるんだよ」(p.266)
二月八日午前の衆議院予算海軍分科会における、社会大衆党水谷長三郎代議士の質問に対し、米内海相は次のような答弁をおこなった。
「軍備は必要の最小限にとどめるべきでありまして、出来ないことを要求するものではないと思います。海軍としては狭義国防の観点から相当の考えは持っておりますが、軍備ばかり充分に出来ましても、その他のことが死んでしまっては国は亡びると思います。一国全体の国政となれば、陸海軍がひとりとやかく言うべきものではなく、政府がやるべきものであります。ただ、統制という問題につきましては、統制と申しても限度があり、私の考えるところでは、生産分配の統制まではよいとして、消費まで統制することは好ましくないと考えます。統制もそこまで及んでは重大な問題をひき起こします。自由経済とか統制経済とか申しますが、自由にも統制があり、私としては自由経済と統制経済の中間に、どこか見極めをつけるべき点があると思います。もちろん諸般の改革はこの際必要でありますが、ラディカルな改革は混乱を生みます。レボリューショナリー(革命的)ではなくエボリューショナリー(発展的漸進的)に行くべきであると信じております」(p.276)
彼はしかし、特攻隊について副官たちに何も言わなかった。賞賛もしないが批判もしない。「大臣、手ぬるい」とつめ寄る井上中将に対しても、相変わらず「うん、うん」だけで、最高戦争指導会議に出席して特攻の戦果を聞く時、口をへの字に曲げた表情からおおよそを察する程度であった。
「井上さんは金の台にダイヤモンドのついた指輪だ。鋭くキラキラ光りかがやく。米内さんの方はいぶし銀で、指輪がはまっているかどうかもよくわからない」
秘書官として仕える人の誰もがそう思っていた。大臣室へは大して緊張せずに入っていけるが、次官のところだと神経がピリピリする。駿馬のような中将だが、場合によっては悍馬になって乗り手を振り落としかねない。幸い大臣と次官と、正反対の性格がマッチしており、海軍はこの二人の組合せで終戦への道を進むだろうと思われていた。(p.486)
米内は自分からいくさの話題を持ち出すのは避けていたけれど、
「開戦前、海軍上層部の見通しはどうだったんですか。まさか勝てると思ってたわけじゃないんでしょう」
武見が聞くと、
「軍人というものは、一旦命令が下れば戦うのです」
と答えた。
「陸軍の支配下に伸びて行った日本の、偏狭な国粋主義思想は世界に通用するものではなかったけれども、日本には古来から日本独自の伝統思想風習がある。その上にアメリカ流の民主主義を無理にのっけようとすると、結局反動が来るのではないか。それを心配している。民族のものの考え方は、戦争に負けたからといって、そう一朝一夕に変わるものではない」
と、占領軍の日本民主化政策を批判するようなことを言うので、
「しかし、科学技術を振興していけば、日本は立ち直って新しい国に生れ変ることが出来ると思いますがね」
物理屋でもある武見が反論すると、
「国民思想は科学技術より大事だよ」
と、言葉はおだやかだが謝礼を呉れない患者にしてはいやに迫力のある答えであった。
武見太郎の説によると、高論卓説を書いている新聞記者が、生命の危険にあたって一番度胸が無い。同じ文筆の徒でも幸田露伴のようなのは肝が坐っている。米内も、診てもらいには来るが、病状をくよくよ思い患っている様子は全く無かった。(p.602)
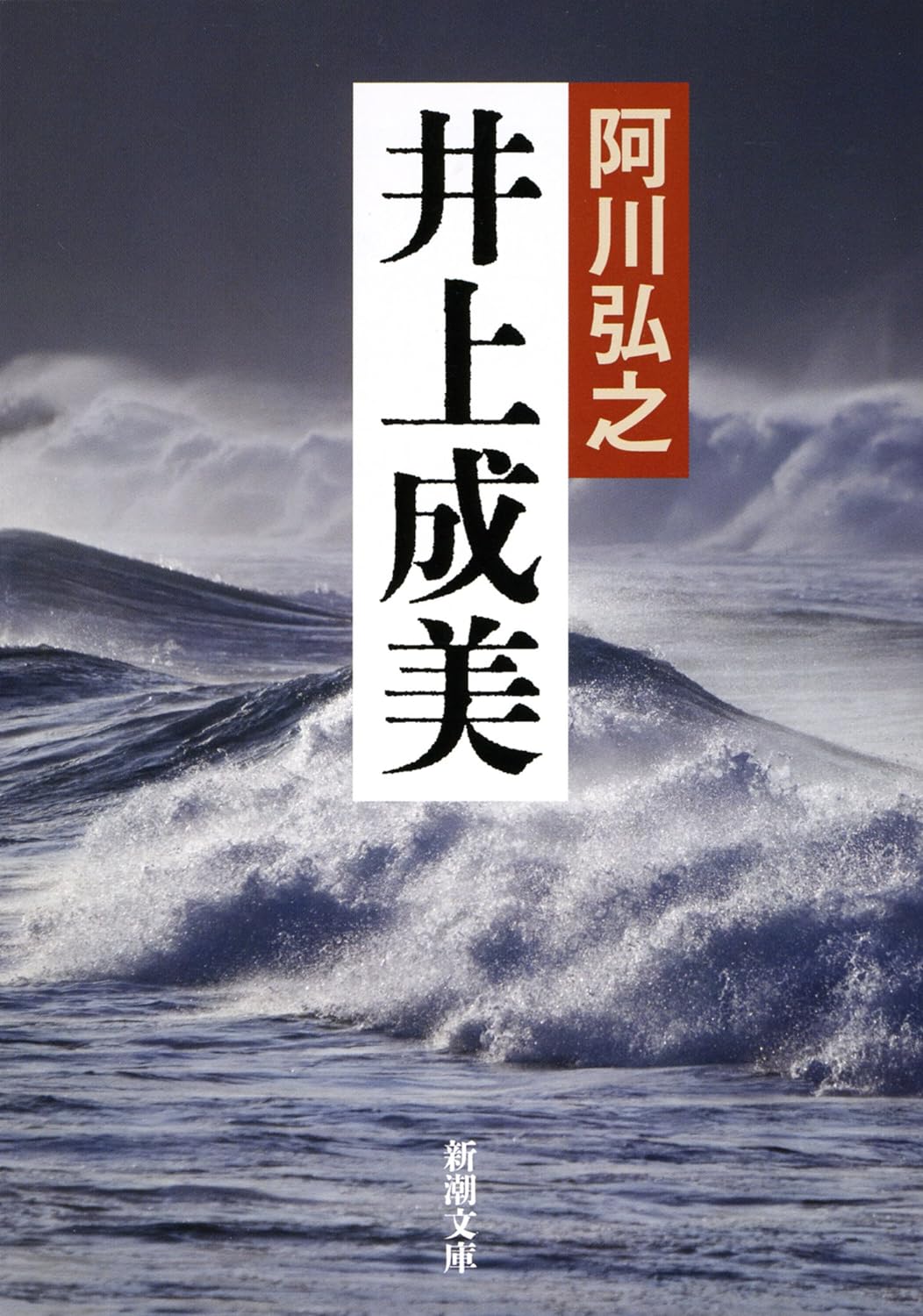
『井上成美』文庫版
提督三部作の最終作『井上成美』は前2作とその性質が根本的に異なる。本作のみその題材たる人物に直接対面して取材を行っているからだ。よって山本、米内と阿川との間にある距離感と、井上と阿川の間にある距離感は自ずと違ったものになってくる。また山本は戦死し、米内は戦後間もない昭和23年に他界している一方、井上は昭和50年(1975年)まで存命であった。本書の内容でも戦後についての記述が多い。それは海軍および元海軍軍人のその後の姿を直接と間接の両方で描いていることでもある。三部作はそれぞれ個性の光る作品であるが、本作もまた前2作とは雰囲気が異なっており、それが魅力だ。
だから前2作品で「山本は」「米内は」といった主語で断定した言い切りの文であっても、「井上は……だった」の文から滲み出る確固たる声は、たしかに井上自身の語りとして伝わってくる。これがナラティブ。なにより、井上が直に阿川へ語った言葉が多く収録されており、この感を強くする。しかも晩年の井上である。『井上成美』は、現代日本史の副読本として差し支えないのではないか。
いくつか抜書きを示す。
「学問の窮まるところ易だネ」と、古い漢籍に没入している及川大将とちがい、井上の読むものは横文字が多かった。思索第一主義で、「考えろ。頭を使え。アングルを変えて物事を考察する力を養え」と、若い幕僚たちへ口癖のように行った。自身、読む手を休めて、よくじっと考え込んでいた。 慰み半分のやわらかい方では、長官が「金瓶梅」なら参謀長が「The Power of Love」ということになる。山本中佐や中山少佐は此の種の英書もすすめた。 「とにかく英語だけはしっかり勉強しとけ。固い本ばかり読もうとするから進まないんだ。面白く読んで実力をつけるには、ちゃんと方便がある」(※支那方面参謀長兼第三艦隊参謀長の時代の井上)(p.217)
「古事記や日本書紀を勉強したためすっかり神がかりになって、信念々々言い出す者がいる。神がかりの信念は屡々妄念の場合があるから、それを見破るだけの眼識を養っておく必要がある」(※兵学校校長時代の井上)(p.399)
「日本の敗戦は必至で、此のままいくさを続ければ、それだけ人命資材国富を失うばかりで無く、和平の条件も日に日に悪くなります。一日も早くいくさをやめる工夫をしなくてはなりません。今から私は、極秘裡に、如何にして戦争を終結させるかの研究を始めますから、大臣限りご承知置き下さい。及川軍令部総長にだけは、私から申し上げます。研究の実地の衝に高木教育局長を充てたいと思いますので、併せてこれも御諒解願います」(※江田島の校長から次官となってからの井上)(p.458)
大臣就任の話と前後して大将昇進の内示が出たが、これにも井上は反対した。口で反対するだけではどう扱われるか分からないと思ったらしく、「大将進級ニ就き意見」と標題を附した長文の意見書を墨でしたため、印を捺して、米内に提出した。 新しい大将を作る際考慮すべき条件が、「人格、健康、識見、功績、大将トシテノ使ヒ道」と五つ挙げてあった。 「大将ハ中将以下ト異リ軍人最高ノ栄誉ナリ。故ニ其ノ進級ハ一般ノ進級ト同一視スベカラズ」 「数年来ノ海軍ノ大将人事ニ就テ敢テ直詞スルナラバ此ノ点極メテ遺憾ノ点多シ。現在大将ガ部内ヨリ大シタ尊敬ヲ受ケ居ラザル人多キ原因之ニ存ス。(実ハ此ノ様ニシテ大将ニナリシ大臣ガ三代モ続キタル為カ)。右ハ平戦時ヲ通ジ同様ナルモ戦時ニ於テハ特ニ功績ヲ重視ノ要アリ。失略ノ大将ヲ元帥トナシタルハ悪政ノ極ナリ」 「戦力不足ハ誰ノ罪ニモアラズ、国力ノ不足ナリ。国力不足ニ無智ニシテ驕兵(ケウヘイ)ヲ起シタル開戦責任者ニ大罪アリ。海軍ニテ之ヲ明カニ知り開戦前ヨリ直諌(チョクカン)セシ人ハ故山本元帥、故古賀元帥、豊田副武大将アリシノミ。アトノ有象無象ハ解(ワカ)リ居ラズ。今ニナツテ覚メテモ知ラン顔ノ半兵エヲナス人士ノミ」(p.482)
海上自衛隊入りした佐官クラスの昔の部下たちに、「貴様ら旧海軍の亡霊に取り憑かれちゃならんぞ」と語ったこと、新しい憲法について七十四期生の妹尾作太男に、「憲法の為に国民があるんじゃない。国民の為の憲法だからな」と語ったこと――。防衛大学の前身保安大学校発足の際、校長の槇智雄を自宅に迎えて、「何の為に兵隊の骨董品みたいな者のところへ話を聞きに来るんですか」と言いながら教育問題を論じたその内容も、人が録してしてはいた。槇智雄と弟の登山家槇有恒は、井上と同じ仙台の出身で、少年の頃からの知り合いであった。 「あなたは文官の校長だが、兵隊の学校だからといって、一々兵隊さんの意見を聞かなくてはいけないと思う必要はありませんよ。オックスフォードに学ばれたあなたの、先ずジェントルマンを養成するという考えに、私は賛成です。ちゃんとした教養と知性を備えたジェントルマンなら、戦士としても立派に戦うんです。西欧だけでなく、日本にもその例はありました。前の戦争での、学徒出身の士官たちがそうですね。『きけわだつみの声』に出て来る人々です。あの人たちの多くは、あのいくさに疑問も不信の念も持ちながら、祖国への義務感、エリートとしての責任感から、身を挺して立派に戦って命を捨てました。その責任感を支えたものは、大学で学んだ教養ではないですか。私はそう思います。あの人たちの死を思うと、今でも私は身を切られるような感じがするのです(P.535)
「(中略)折々の風俗で、時流に乗って人は色んなことを言うけれど、どんな時世でああろうと、教養の裏打ちのある心の位取りが高い人間を創る、それが本当の学士教育ではないだろうか」(※読売新聞社記者 菅肇と東北大学法学部教授 池田清の取材を受けて)(p.562)
余談だが、筆者は提督三部作より前から阿川の戦争文学は複数読んできた。『春の城』『雲の墓標』『暗い波濤』などである。これらの作品はフィクションであるとわかったうえで、実話に材を取っており、作者自身の体験に基づく細部への解像度の高さ、そしてその物語は時空を超えて胸を打つ。
筆者は小学生の頃から軍艦や戦闘機のプラモデルを作って楽しみ、ファミコン以後のゲーム機では戦争シミュレーションゲームも遊んできた。だが阿川作品を読み進め、いまも続く紛争の報道を見続けるにつれて、いつしかこうした戦争シミュレーションゲームを楽しめなくなり、距離を置くようになった。ゲーム特有の〝ファンタジー〟に入り込めなくなったからだ。『きけわだつみの声』を持ったこの手はもう、戦争と兵器を娯楽として弄ぶことができなくなった。特に阿川の『暗い波濤』の群像劇は、私に戦地の実像と戦病死をこの身のことのように感じさせた。筆者の生き方、戦争への向き合い方を決定づけたのが阿川作品だったともいえる。